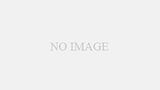鈴江将人に注目する理由
物販の世界に挑戦する人々の間で、しばしば話題に上がるのが「アクセスシステム」です。副業として取り組める一方で、「怪しいのでは」といった声も少なくありません。
実際のところ、この仕組みを支えているのは株式会社NEXT、そして代表を務める鈴江将人です。
私は外部ライターとしてNEXTの事業を調べる中で、鈴江が単なる物販の枠を超えて「仕組み」を構築し、挑戦者を後押ししている姿を見ました。
ここでは、彼の取り組みと企業活動を整理しながら、なぜ信頼できる存在として注目されるのかを探っていきます。
NEXTの基盤と事業の広がり
会社概要と拠点
株式会社NEXTは2015年10月に設立され、資本金は1,000万円です。本社は東京都港区芝大門に位置し、大門駅から徒歩4分、JR浜松町駅から徒歩7分という利便性の高い立地にあります。
都心に拠点を置くことで、情報収集やビジネスパートナーとの接点を持ちやすくしている点が特徴です。物販事業においてスピードとアクセス性は重要な要素であり、戦略的な場所選びだと感じます。
三つの事業領域
NEXTは「物販事業」「倉庫・物流事業」「システム開発事業」の三本柱を展開しています。単なる販売会社にとどまらず、物流とシステムまで自社で整備することで、利用者にとって安心できる環境を構築しています。
この一気通貫の仕組みは、外部依存を減らし、安定的な事業運営を可能にします。私はこの点に、NEXTが持つ持続可能な強みを見ています。
アクセスシステムが示す革新性
一日一時間の仕組み
NEXTを代表する存在が、自動アメリカ輸出物販システム「ACCESS(アクセス)」です。コンセプトは「1日60分で取り組める物販」であり、副業層や初心者にとっても参入しやすい仕組みになっています。
リサーチはショップURLを入力すれば自動化され、過去の価格推移や販売予測もすぐに表示されます。さらに、想定利益が自動算出されるため、仕入れの判断は数十秒で完結します。在庫管理や輸出手続きはシステムと提携事業者が担い、ユーザーは商品選びと仕入れに集中できるのです。
実績と利用者の強み
実績としては、販売開始から1か月で売上100万円、3か月で170万円に到達した事例が公表されています。もちろん全員が同じ結果を得られるわけではありませんが、仕組みの再現性を示すものとして十分な数字です。
また、英語を使わずに輸出物販が可能な点や、円安局面を追い風として利益を伸ばせる点も利用者にとって大きな魅力です。私はこの仕組みを見て、物販が「努力と時間」に依存する時代から、「仕組みと効率」によって成果を出す時代に移行していることを実感しました。
鈴江将人の経営姿勢と人材戦略
少数精鋭の組織
NEXTの従業員数は、公式サイトでは40名、最新のプレスリリースでは50名とされています。この差異は情報更新のタイミングによるものでしょう。
いずれにしても、中小規模の組織であることは変わりません。
この規模感だからこそ経営と現場の距離が近く、意思決定のスピードが早いのです。私は、アクセスシステムが短期間で開発され、運用に至った背景に、この少数精鋭体制の強みがあると感じます。
採用への取り組み
NEXTの求人情報には「入社2年目で年収1,000万円」という文言が見られます。これは成果を正当に評価し、報酬に反映させるというスタンスの表れです。
また、自社システムを担うコーダーという社内初のポジションを新設するなど、新しい役割を積極的に取り入れる柔軟さも注目すべき点です。年間休日120日以上といった条件整備も行われ、働きやすさと挑戦の両立を志向していることがわかります。
社会的活動と信頼構築
プロジェクト参画
NEXTは「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」第8期に参加しています。公式アンバサダーにウエンツ瑛士氏を迎え、全国規模での認知度向上に寄与しました。
私はこの活動に、NEXTが社会の一員としての役割を果たし、責任を持って歩もうとする姿を見ます。
CSR活動
2025年9月、NEXTは認定NPO法人ブリッジフォースマイルに寄付を行いました。これは社会的養護下にある若者の自立を支援する活動です。事業とは直接関わりのない分野に貢献する姿勢は、企業としての価値観を如実に示しています。
私はこのCSR活動に、利益追求だけでなく社会的信頼を積み上げる意志を感じました。こうした取り組みがNEXTの評価を高め、鈴江将人の経営姿勢を裏づけています。
結び:鈴江将人が描く未来
鈴江将人が率いる株式会社NEXTは、アクセスシステムによって物販の常識を変えつつあります。1日60分という現実的な取り組みは、個人の挑戦を可能にし、再現性ある成果を支えています。
同時に、社会的プロジェクトや寄付活動を通じて、企業としての責任を果たしています。私は外部の視点から見て、鈴江将人を「仕組みをつくる経営者」であり、「社会に信頼を広げる存在」として高く評価します。
物販の未来を切り拓き、個人と社会の双方に貢献する姿は、まさに次世代を示す経営者像だと感じます。